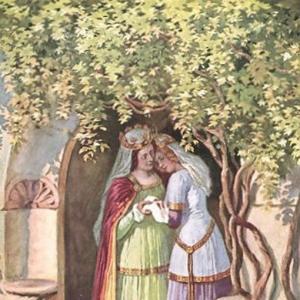読書の時間: 2 分
「群れにえさをやるのにどこが一番好きかい?」と男が年とった牛飼いに言いました。「ここですよ、だんな、草が良すぎでも悪すぎでもないところですよ。でないと駄目です。」「どうして駄目なんだ?」と男が尋ねました。「あそこの草原からあの憂鬱な鳴き声が聞こえますか?あれはサンカノゴイですよ。サンカノゴイは昔牛飼いでした。ヤツガシラもそうでした。こんな話ですよ。サンカノゴイは群れを花がたくさん生えている豊かな緑の草原に放しました。それで牛たちは荒々しくて手に負えなくなりました。ヤツガシラは高いやせ地の山に牛を駆り立てました。そこでは風が砂と遊び、牛たちはやせて力が無くなりました。夕方になって牛飼いたちは牛を帰らせようとしましたが、サンカノゴイは二度と牛を集められませんでした。牛たちはあまりに元気がよすぎて逃げてしまったんですよ。サンカノゴイは『来い、牛よ、来い、』とよびましたが、無駄でした。牛は呼び声に全然注意しませんでした。だけど、ヤツガシラは牛たちの脚を立たすことすらできませんでした。とても弱ってしまったんですよ。『立て、立て、立て』とヤツガシラは叫びましたが、無駄でした。牛たちは砂にねたままでした。人がほどほどにやらないときそうなるんです。それで、今日まで、今は監視する群れもないけれどもサンカノゴイは『来い、牛よ、来い』と鳴くし、ヤツガシラは『立て、立て、立て』と鳴くんです。」
 言語を学びましょう。単語をダブルタップしてください。Childstories.org と Deepl.com で文脈の中で言語を学びましょう。
言語を学びましょう。単語をダブルタップしてください。Childstories.org と Deepl.com で文脈の中で言語を学びましょう。背景情報
解釈
言語
このグリム兄弟のメルヘンは、サンカノゴイとヤツガシラという二つのキャラクターにまつわる寓話的な物語です。ここでのサンカノゴイとヤツガシラは、象徴的に不適切な管理と極端な行動の結果について教訓を与える役割を担っているようです。
物語の中で、サンカノゴイとヤツガシラはどちらも牛飼いですが、それぞれ異なる過ちを犯します。サンカノゴイは牛を栄養豊かな草原に放つことで牛たちを手に負えなくし、ヤツガシラは高いやせ地の山に追いやることで牛の力を奪います。この対比は、何事も極端に偏ると問題を引き起こすことを示唆しています。
この物語から得られる教訓は、物事には「ほどほど」が大切であるということです。過度に恵まれた環境も、厳しすぎる環境もどちらも問題を引き起こし得るため、バランスを取ることの重要性を説いています。そして、過去の過ちを引きずり続けることの愚かさも暗に示されています。サンカノゴイとヤツガシラは、それぞれの過去の行動の結果から学んでいないため、その声は今でも空しく聞こえているという描写です。
このように、グリム兄弟の物語は単なるエンターテインメントにとどまらず、教訓を含んだ深い意味を持っています。
この物語は、グリム兄弟によるメルヘンの一つであり、二人の異なる牛飼いの失敗と、それが後に彼らの化身となった鳥たちの話を伝えています。
物語の主なテーマは「中庸」や「バランス」です。サンカノゴイが群れを非常に豊かな草原に放った結果、牛たちは制御不能になるほど元気になり、逃げ出してしまいました。一方で、ヤツガシラは群れを痩せた高地に追いやったため、牛たちは力を失い動けなくなってしまいました。それぞれの結果として、サンカノゴイは「来い、牛よ、来い」と鳴き、ヤツガシラは「立て、立て、立て」と鳴きます。
このような物語は、極端な選択や行動は、どちらも問題を引き起こすことになり得るという教訓を伝えています。豊かすぎる環境や、貧しすぎる環境のどちらも牛にとって良くないことを通して、人間の生活においても過度や不足を避け、中庸を保つことの重要性が示唆されています。これがこの物語の意図するところであり、教訓的な意味合いを含んでいます。
この物語は、グリム兄弟による寓話的なストーリーで、二人の牛飼い「サンカノゴイ」と「ヤツガシラ」の行動を通して、極端な選択がもたらす結果を示しています。この両者の牛飼いが選んだ対照的な方法が、それぞれ失敗につながる様子を描いています。
サンカノゴイは、牛たちを豊かな草原に連れて行きましたが、あまりにも草が豊富で牛たちは手に負えなくなり、逃げ去ってしまいます。これにより、過剰な豊かさや放任が制御不能につながることを象徴しています。
一方で、ヤツガシラは牛をやせた山地に連れて行きますが、牛たちは栄養不足で力を失い寝たきりになってしまいます。これは、厳しすぎる環境や過度の制限が無力化を招くことを示唆しています。
この寓話は、「ほどほど」や「バランスの取れた選択」が重要であることを教えてくれます。最終的に、サンカノゴイとヤツガシラは、その選択の結果により空しく鳴き続けます。物語は、過度や極端を避け、適度を心がけることが重要であるという普遍的な教訓を伝えています。
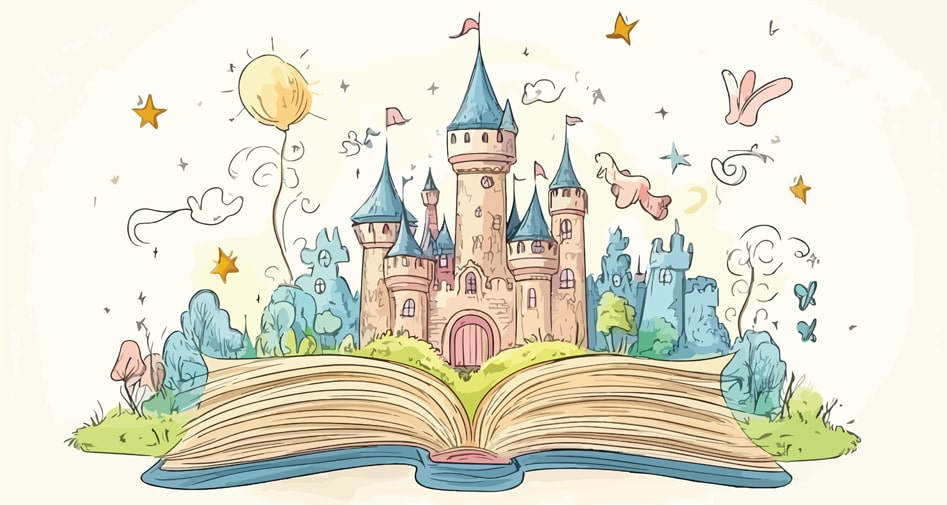
 Facebook
Facebook  Whatsapp
Whatsapp  Messenger
Messenger  Telegram
Telegram